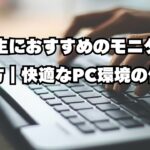【2025年版】大学生向けパソコンの選び方完全ガイド|文系・理系別おすすめと失敗しないスペック【名古屋の学生向けサポート】
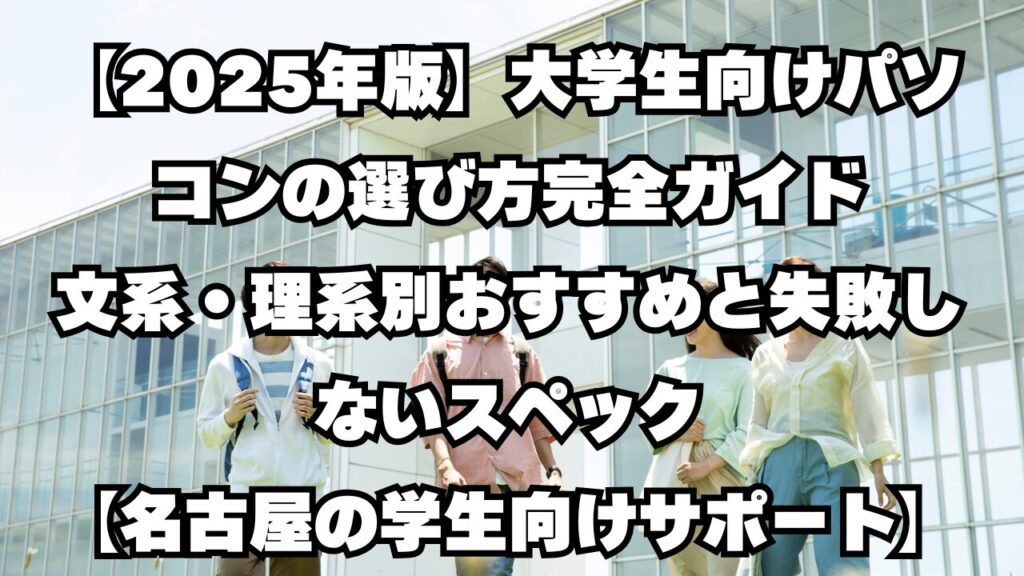
【2025年版】大学生向けパソコンの選び方完全ガイド|文系・理系別おすすめと失敗しないスペック
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!
大学生活を始めるにあたり、ノートパソコンは授業、レポート作成、就職活動に至るまで、あなたの学びを支える最も重要な「相棒」となります。アンケート調査によると、ほとんどの大学生がパソコンを必要だと回答しており、自分専用のPCを持っている人が大半です。
この記事では、入学から卒業までの4年間、またはそれ以降も快適に使い続けられるPCを選べるよう、文系・理系それぞれの視点から必要なスペックを徹底的に解説します。
💡 大学生のパソコン選びは「運転免許を取る車選び」に似ています
大学生のパソコン選びは、運転免許を取って最初の車を選ぶのと同じです。安い中古車(低スペックPC)を買うと、すぐに故障したり(フリーズ)、高速道路で追い越せなかったり(処理速度が遅い)してストレスになります。逆に、街乗りしかしないのに高級スポーツカー(オーバースペック)を買っても、性能を活かせず無駄になります。大切なのは、4年間の大学生活(走行距離)を快適に過ごせる「ちょうどいい1台」を選ぶことです。
この記事を読めば、文系・理系別の最適なスペックがわかり、予算別のおすすめモデルを知り、学割を活用してお得に購入できます。
注:この記事では一般的な大学生活(レポート作成、オンライン授業、研究など)に焦点を当てていますが、専門的なゲーム開発や本格的な4K動画編集などの特殊な用途には、さらに高スペックなモデルが必要です。
⚠️ 選び方を間違えると4年間後悔します
スペック不足のリスク:安さを優先して低スペックモデルを選ぶと、2年目には動作が遅くなり、買い替えが必要になる可能性があります。
重量の問題:重すぎるPCは持ち運びが苦痛になり、結局自宅に置きっぱなしになってしまいます。
バッテリー不足:バッテリーが持たないと、授業中に充電が切れて作業ができなくなります。
大学生にパソコンは必須!選び方を間違えると4年間後悔する
大学生活では、レポート作成・オンライン授業・研究・就職活動など、さまざまな場面でパソコンが必須となります。特にオンライン授業やオンラインテスト、ハイフレックス型授業(対面とオンラインの併用)が普及した現在、パソコンを使う機会はこれまで以上に増えています。
先輩学生の失敗談から学ぶ後悔ポイント
現役大学生へのアンケート調査では、37%以上が購入したPCに不満や失敗を感じていることがわかっています。
💡 パソコン選びの失敗は「靴選びの失敗」に似ています
パソコン選びの失敗は、大学生活で毎日履く靴選びの失敗に例えられます。安いからとサイズの合わない靴(スペック不足)を買うと、毎日足が痛くなり(動作が遅い)、結局買い直しになります。重すぎる靴(重いPC)は、毎日履いて歩くのが苦痛になります。靴底がすぐにすり減る靴(バッテリーが持たない)は、途中で歩けなくなってしまいます。
先輩学生の失敗談TOP3
- 失敗①:スペック不足で2年目に買い替え
「安さ」を優先して低スペックなCore i3未満(例えばCeleron)やメモリ4GB(ギガバイト)のモデルを選んだ結果、文字入力に遅延が発生したり、複数のソフトを立ち上げるとフリーズしてしまい、課題が進まずストレスになった。特に低スペックのパソコンでは、Windowsアップデートが動くだけでパソコンが全く動かなくなる、という問題も起こり得ます。
- 失敗②:重すぎて持ち運ばなくなった
大学生活では、授業や図書館、カフェなど学外でPCを使用する機会が非常に多くなります。15インチを超えるような重いPCを購入したため、持ち運びが億劫になり、結局自宅に置きっぱなしになってしまった。重いパソコンは、毎日1.5リットルのペットボトルをカバンに入れて移動するようなものです。
- 失敗③:バッテリーが持たない
コンセントが席ごとに設置されていない講義室や、図書館での長時間作業を想定せずに購入した結果、「授業中に充電が切れて作業ができなくなり、困った」という失敗談も多数。
【最重要】大学生がチェックすべき5つのスペック
パソコンの価格や見た目よりも、「CPU」「メモリ」「SSD」という基本スペックが、あなたの4年間の快適さを決定づけます。
①CPU(中央演算処理装置):Core i5 / Ryzen 5以上を推奨
CPUはパソコンの全ての処理を司る「頭脳」です。性能が高いほど、複雑な計算やマルチタスク(複数アプリの同時起動)がスムーズになります。
💡 CPUは「人間の脳の処理速度」のようなもの
CPUは人間の脳の処理速度に例えられます。処理速度が遅い脳(低スペックCPU)では、簡単な計算(文書作成)はできても、複雑な問題(複数アプリの同時起動)を解こうとすると時間がかかり、フリーズ(思考停止)してしまいます。処理速度が速い脳(高スペックCPU)なら、複数の問題を同時に素早く解決できます。
Core i5 / Ryzen 5:推奨(文系・理系共通)
性能:インターネット閲覧、Office作業、軽いマルチタスクを快適にこなす
対象:4年間使うことや将来のOSアップデート(Windows 12など)を考えると、最もコスパが良い
推奨世代:Intel第13世代Core i5以上、Ryzen 7000番台以降
Core i7 / Ryzen 7:理系・専門用途向け
性能:データ解析、CAD、動画編集など高度な作業をスムーズに実行
対象:工学系、情報系、クリエイティブ系の学生
⚠️ Core i3未満(Celeron、Pentiumなど)は避けるべき
Core i3未満のCPUは、動作が遅くなるため、4年間使うことを想定している大学生には不向きです。特にWindowsアップデートが動くだけでフリーズする可能性があります。
②メモリ(主記憶装置):最低8GB、できれば16GB
メモリ(RAM)は、CPUが作業を行うための「作業机の広さ」に例えられます。机が広いほど、Word、ブラウザ(タブ多数)、Zoomといった複数のソフトを同時にスムーズに動かすことができます。
💡 メモリは「図書館の閲覧席」のようなもの
メモリは図書館の閲覧席に例えられます。小さい席(8GB)では、教科書1冊、ノート1冊しか広げられず、参考書を見るには教科書をしまわなければなりません(アプリの切り替えが遅い)。大きい席(16GB)なら、教科書、ノート、参考書、辞書を全部広げても余裕があり、スムーズに勉強(作業)できます。
8GB:最低限
用途:レポート作成やオンライン授業、軽いマルチタスク
デメリット:Webブラウザでタブを10個以上開いたり、複数のアプリを同時起動すると動作が重くなる可能性が高い
16GB:推奨(2025年の必須条件)
用途:複数のアプリケーション(Word、Excel、Zoomなど)を同時に使用するマルチタスク
メリット:4年間快適に使え、将来のOSアップデートにも対応
⚠️ メモリは後から増設できない場合が多い
近年のノートPCは薄型化のため、メモリが後から増設できない機種が多いです。そのため、購入時に16GBを搭載しておくことを強くおすすめします。予算を削って8GBモデルを選び後悔するよりも、最初から16GBを選ぶ方が賢明です。
③ストレージ(外部記憶装置):SSD 256GB以上必須、512GB推奨
ストレージはデータやアプリを保存する「倉庫」です。
💡 SSDは「新幹線」、HDDは「各駅停車」
ストレージの種類は、電車の速度に例えられます。HDD(ハードディスク)は各駅停車で、目的地(データ)に到達するのに時間がかかります。SSD(ソリッドステートドライブ)は新幹線で、目的地に一瞬で到着します。パソコンの起動やアプリの立ち上がりが劇的に速くなるため、SSDは絶対に必要です。
SSD 256GB:最低限
注意点:OSやアプリケーション、セキュリティアップデートで容量を消費するため、256GB未満ではすぐに容量不足になるリスク
SSD 512GB以上:推奨
メリット:4年間の利用と、レポート、授業資料、写真、アプリの増加を見越すと、容量不足の心配が少ない
⚠️ HDDのみのモデルは絶対に避けるべき
HDD搭載モデルは起動や保存が遅く、日常的なストレスの原因となります。SSD搭載モデルを選ぶことは絶対に譲れない条件です。
④重量:1.3kg以下が理想、最大1.5kg
大学生はパソコンを毎日持ち運ぶ機会が多いです。
⚠️ 1.5kgを超えると持ち運びが苦痛になる
1.5kgを超えると、毎日1.5リットルのペットボトルをカバンに入れて移動するようなもので、持ち運びが苦痛になりやすいという先輩の失敗談が多くあります。
⑤バッテリー駆動時間:実測8時間以上
講義や図書館、カフェなど、電源のない場所で作業する機会を想定すると、バッテリーの持ちは非常に重要です。
💡 バッテリー駆動時間は「スマホの電池持ち」のようなもの
バッテリー駆動時間は、スマホの電池持ちに例えられます。カタログに「24時間」と書いてあっても、実際に動画を見たりゲームをしたりすると、半日も持たないことがあります。パソコンも同じで、カタログ値(公称値)は最低限の負荷での数値なので、実際の使用時間(実測値)は7割程度、または半分程度になります。
バッテリー駆動時間の選び方
- 推奨基準:カタログ値で8時間以上。これにより、実働で6〜8時間程度の作業が可能となり、1日中図書館などで使いたい学生にとって安心
- 公称値と実測値の差:メーカーが公表するカタログ値は、最低限の負荷で測定されるため、実際の使用時間は公称値の7割程度
【文系・理系別】学部・専攻別の推奨スペック早見表
学部や専攻によって、必要とされるPCのスペックは大きく異なります。特に、専門ソフトウェアの利用有無がCPUやメモリの推奨基準を決定づけます。
💡 学部別スペックは「職業別の道具」のようなもの
学部別のスペック選びは、職業別の道具選びに例えられます。料理人(文系)には包丁とまな板(基本スペック)があれば十分ですが、大工(理系)にはノコギリ、ドリル、電動工具(高スペック)が必要です。医者(医療系)には専用の手術器具(専門ソフト対応)が必要で、芸術家(クリエイティブ系)には最高級の画材(最上位スペック)が必要です。
文系(文学・法・国際教養等)
CPU:Core i3 / Ryzen 3でも可、Core i5 / Ryzen 5推奨
メモリ:8GB
ストレージ:SSD 256GB
主な用途:Word、Excel、PowerPointでのレポート・プレゼン作成、文献調査
社会科学系(経済・経営・社会等)
CPU:Core i5 / Ryzen 5
メモリ:8GB〜16GB推奨
ストレージ:SSD 256GB〜512GB
主な用途:統計解析ソフト(SPSS、R)、大規模データ分析(Excel)
理系(機械・物理・化学・農学等)
CPU:Core i5 / Ryzen 5、Core i7 / Ryzen 7推奨
メモリ:16GB以上
ストレージ:SSD 512GB
主な用途:プログラミング(Python, C, MATLAB)、データ処理、シミュレーション、統計解析(R)
工学系(建築・情報・電気等)
CPU:Core i7 / Ryzen 7(第12世代Core以上を推奨)
メモリ:16GB以上必須
ストレージ:SSD 512GB〜1TB
グラフィック:専用GPU(CADを扱う場合)
主な用途:3D CAD(AutoCAD, SolidWorks)、仮想環境、プログラミング
医療・看護系(医学・看護・薬学)
CPU:Core i5 / Ryzen 5、Core i7推奨
メモリ:8GB、16GB推奨
ストレージ:SSD 256GB〜512GB
主な用途:実習記録作成、医学統計、オンライン学習。タブレットとの併用も有効
クリエイティブ・デザイン系(芸術系)
CPU:Core i7 / Ryzen 7以上
メモリ:32GB以上推奨
ストレージ:SSD 1TB推奨
グラフィック:専用GPU(RTX 4060以上)
主な用途:4K動画編集、3DCG(Blender, Maya)、Adobe Creative Suite(Photoshop, Premiere Pro)
⚠️ MacとWindowsの選択に注意
芸術系や情報系の一部ではMacが使われますが、理工系では専門ソフト(CAD、数値計算ソフトなど)の互換性や大学の授業でのサポート体制の関係でWindowsが推奨または必須となるケースが多くあります。必ず入学予定の学部の指定を確認しましょう。
予算別おすすめノートパソコン【2025年最新】
大学生が購入するパソコンの価格は、エントリークラスで5万円〜9万円、ミドルクラスで10万円〜15万円、ハイスペックモデルで15万円以上が相場となっています。長く快適に使うことを考えると、10万円前後のミドルクラスの予算設定が最もおすすめです。
予算7〜10万円:コスパ重視の文系モデル
主にレポート作成、オンライン授業、Web閲覧が中心の文系学生や、コストを抑えたい理系学生の最低限のラインです。
Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10
スペック:Ryzen 5 7530U / 16GB / SSD 512GB / 14型 FHD
価格:7万円台(税込)
特徴:7万円台でメモリ16GBを確保しやすいコスパ最強モデル。日常使いに快適な性能
不向き:3D CADや機械学習など高負荷な理系専門ソフトの利用
mouse A4-A5U01SR-B
スペック:Ryzen 5 7430U / 8GB / SSD 256GB / 14型 FHD
価格:79,800円(税込)
特徴:安価でありながらRyzen 5を搭載し、Office作業には十分な性能。国内生産で安心
不向き:メモリが8GBのため、Webブラウザでタブを大量に開くマルチタスクや動画編集
予算10〜15万円:万能バランスモデル
Core i5/i7、メモリ16GB、SSD 512GBを基本とし、文系・理系問わず、長く快適に使いたい学生に最適な価格帯です。大学4年間で性能不足になるリスクを最小限に抑えられます。
HP Pavilion Aero 13-bg
スペック:Ryzen 5 8640U / 16GB / SSD 512GB / 13.3型 FHD
価格:12万円台(学割適用後の価格を想定)
特徴:超軽量(1kg前後)で高性能CPU(Ryzen 5)を搭載しており、携帯性を最優先したい学生に最適
不向き:独立したGPUが必要な本格的な3DCG制作や大規模な機械学習
ASUS VivoBook 15
スペック:Core i5-1240P / 16GB / SSD 512GB / 15.6インチ
価格:約11.2万円〜(税込)
特徴:Core i5(Pシリーズ)搭載で処理能力が高く、16GBメモリでマルチタスクに強い
不向き:毎日持ち運ぶには15.6インチは重く、据え置き利用が中心の方
予算15〜20万円:ハイスペック理系・クリエイター向け
主に理工系(特に情報、機械、建築系)、芸術系など、高負荷な専門ソフトの利用が必須となる学生向けです。
Lenovo Yoga Slim 7i Gen 10
スペック:Core Ultra 7 / 16GB / SSD 1TB / 14型 WUXGA
価格:16万円台〜(学割適用後の価格を想定)
特徴:Core Ultra搭載で高性能とバッテリー効率を両立。AI処理に強く、プログラミングやデータ解析にも対応できる万能機
不向き:4K動画編集や大規模な3Dモデリングなど、最上位の専用GPUが必要な用途
mouse K5-I7G50BK-B
スペック:Core i7-12700H / 16GB / SSD 1TB / RTX 2050 / 15.6型 FHD
価格:18万円台〜(税込)
特徴:専用GPU(グラフィックボード)を搭載しており、CADソフトや軽い動画編集、機械学習の基礎学習にも対応
不向き:ゲーミングPCに近い重量(約2.0kg前後)になるため、毎日大学に持ち運びたい方
Microsoft Officeは必要?学生の賢い選択
レポート作成やプレゼンテーションにおいて、Word、Excel、PowerPointといったMicrosoft Office製品は、図表のフォーマット指定やデータ処理のため、大学生活に必須のソフトです。
Officeの購入形態3パターン
①PC付属版
メリット:購入後すぐに使える。セット価格で単体購入より割安になることが多い
デメリット:PC本体にライセンスが紐づくため、PCを買い替えても移行できない
②Microsoft 365サブスク
メリット:常に最新版を利用でき、PCを買い替えてもライセンス移行が可能。複数台のデバイスで利用可能
デメリット:継続的な費用が発生する
③大学無償提供(Office 365 Education)
メリット:費用負担ゼロでWord、Excelなどが使える
デメリット:卒業と同時に使用できなくなる。大学の在学期間中に限定される
⚠️ 学生の賢い選択
多くの大学ではOffice 365 Educationが無料で提供されているため、まずは大学のライセンス提供の有無を入学前に確認し、無償提供がある場合はOfficeなしモデルのPCを選ぶことで、本体費用を抑えることができます。
卒業後の使用を見据える場合は、社会人になってからサブスクリプションを契約するか、買い切り版を購入することを検討しましょう。
無料の代替ソフト
無料の代替ソフト
- Google Workspace(Googleドキュメント、スプレッドシート、スライド):クラウド上でリアルタイムの共同編集が可能であり、グループワークでの連携に非常に役立つ
- 注意点:これらの無料ソフトや互換ソフト(LibreOfficeなど)は、Officeと互換性があるとされていますが、Officeで作成された複雑なレイアウトや図表が崩れたり、機能が使えなかったりするリスクがある。レポート提出の際に教授の指定フォーマット通りに表示されないといったリスクを避けるため、Officeが使える環境を確保することが推奨される
学割・キャンペーンを最大限活用する方法
大学生は学割(アカデミック版割引)を利用して、通常価格よりも大幅にお得にパソコンを購入できます。学割の割引率はメーカーやモデルによって異なりますが、数万円の差が出ることもあります。
💡 学割は「学生の特権」
学割は、映画館の学生料金やテーマパークの学生割引と同じ「学生の特権」です。一般料金(通常価格)で買うよりも2〜3万円安く買えることもあるので、使わないと損です。ただし、学割は公式サイト限定が多く、家電量販店では使えないことが多いので注意しましょう。
主要メーカーの学割プログラム
主要メーカーの学割
- Apple(アップル):学生・教職員向けストアを通じて、MacBookやiPadを教育価格で購入できる。デザイン系やクリエイティブな分野でMacを検討している方は必見
- Microsoft(マイクロソフト):Surface製品が最大10%OFFになる学割を提供
- Dell(デル)、HP(ヒューレット・パッカード)、Lenovo(レノボ):公式オンラインサイトで学割キャンペーンや学生ストアを開設しており、割引価格でカスタマイズモデルを購入できる
⚠️ 学割の適用場所
学割価格での購入はメーカーの公式サイト限定キャンペーンであることが多く、家電量販店の店頭では実施されていない場合があります。割引を最大限に活用したい場合は、公式サイトの学生向けストアから購入を検討しましょう。
購入時期(新入生向けキャンペーン)
大学生向けのパソコン購入の最もお得な狙い目は、新学期前の1月、2月、3月です。
⚠️ 3月は配送が混雑
3月は配送が混雑し、人気モデルは在庫不足や納期遅延のリスクが高まるため、1月〜2月上旬に購入を完了させるのが最適です。
名古屋の家電量販店での学割対応状況
名古屋市内の家電量販店(ビックカメラやエディオンなど)では、学割価格を適用できるケースは少ないですが、実機を触って確認できるという大きなメリットがあります。
おすすめの戦略:実際に店頭でキーボードの打ちやすさや画面の見やすさ、持ち運んだときの重さを体感し、その後、メーカー公式オンラインストアやネット通販で学割価格を適用して購入する、という方法がおすすめです。
持ち運びに便利な周辺機器・アクセサリー
大学生はPCを毎日持ち運ぶことが前提となるため、本体と合わせて周辺機器を揃えることで、快適性と安全性が大幅に向上します。
必須・推奨の周辺機器
- ノートパソコンケース/スリーブ(必須):予算3,000円〜5,000円。頻繁な持ち運びによる衝撃や落下から本体を保護するために、クッション性のあるものが必須
- ワイヤレスマウス(推奨):予算2,000円〜5,000円。タッチパッドでの長時間作業は疲労の原因となる。ロジクールなどの使いやすくコスパの良いモデルがおすすめ
- USB-Cハブ(必須):予算3,000円〜7,000円。薄型ノートPCやMacBookはポート数(端子)が少ないため、USB-A、HDMI出力、SDカードスロットなどが使えるUSB-Cハブ(変換器)があると便利
- 外付けSSD/USBメモリー(必須):予算5,000円〜10,000円。レポートやプレゼン資料のバックアップや、大容量データの持ち運び、容量不足の補完に必要
- ノートパソコンスタンド(推奨):予算2,000円〜4,000円。長時間の作業時に視線の高さを調整でき、姿勢が悪くなるのを防ぎ、疲労軽減に役立つ
- モバイルバッテリー(推奨):予算8,000円〜15,000円。授業中にバッテリーが切れた際、USB PD(Power Delivery)対応のモバイルバッテリーがあれば充電できる
初期設定が不安な新入生へ
大学入学後、パソコンを箱から出して最初に行う初期設定は、4年間の快適さやセキュリティに大きく影響します。
初期設定の流れ概要
所要時間:通常1〜2時間程度で完了します。
名古屋市内での学生向け初期設定サポートサービス
自分で初期設定を行うのが不安な方や、すぐに授業で使いたい方は、専門業者によるサポートサービスの利用を検討できます。
サポートサービスの選択肢
- 家電量販店の初期設定サービス:名古屋市内の主要な家電量販店では、有料で初期設定やデータ移行サービスを提供
- 専門サポートサービス(PCホスピタル等):専門のパソコン修理業者やサポート業者は、初期設定だけでなく、故障時の修理やトラブル対応も行ってくれる。名古屋市内にも対応している業者へ相談することで、対面または遠隔(リモート)で安心してサポートを受けられる
よくある質問(FAQ)
Q1: MacとWindowsどっちがいい?
A: 学部の指定がなければ、Windowsの方が無難で汎用性が高いです。理系や工学部では、CADや専門的な開発ソフト(Visual Studio, MATLABなど)がWindows専用である場合や、実験機器との互換性の関係でWindowsが有利な場合が多いです。Macはデザインや映像編集、クリエイティブ系で非常に人気が高く、文系学生や国際教養系であればMacBook Airも快適に利用できます。基本的には大学の指定を最優先しましょう。
Q2: 中古パソコンはおすすめ?
A: 予算を抑えたい文系学生の基本的な用途であれば、信頼できる販売店で保証付きの中古PCを購入することは可能です。しかし、理系や情報系の学生には、最新の専門ソフトウェアの動作要件を満たせないリスクがあるため、初心者には新品が推奨されます。中古PCはバッテリーやSSDの劣化、保証が短いなどのリスクがあるため、購入前にバッテリー残存や保証内容を必ず確認が必要です。
Q3: メーカー保証は延長すべき?
A: 延長保証(有償保証)は強く推奨されます。大学生はPCを持ち運ぶ機会が多いため、落下や水濡れといった偶発的な事故(ユーザー過失による故障)のリスクが高いです。生協推奨モデルでは、4年間の保証や動産保険、修理期間中の代替機貸出などが含まれているため、安心感があります。
Q4: タブレットとノートPCの違いは?
A: ノートPCはレポート作成やプログラミングといった文字入力が不可欠な作業に必須です。タブレットは講義資料への書き込みやノート取り、電子教科書の閲覧といった用途に優れており、特に医療・看護系ではタブレットとの併用が推奨されますが、パソコンの補助ツールとして考えるべきです。iPadやAndroidタブレット、Chromebookは、大学が求める必須スペックのパソコンの代替にはならないことに注意が必要です。
Q5: 何年くらい使える?
A: パソコンの平均的な寿命は3〜5年とされています。しかし、Core i5/Ryzen 5以上、メモリ16GBといった余裕を持ったスペックを選び、適切にメンテナンスすれば、4年間の大学生活から卒業後の仕事まで快適に使い続けることが可能です。
Q6: 名古屋で実物を見て買えるお店は?
A: 名古屋市内では、名古屋駅周辺の大型家電量販店(ビックカメラ、エディオンなど)や、大須商店街周辺の中古/専門PCショップなどで、多くの機種の実機を確認することができます。名古屋大学の学生が自由に使えるPC教室(サテライトラボ)も学内に設置されており、Officeソフトの操作などを試すことができます。
Q7: 学割やキャンペーンはいつが狙い目?
A: 新入生向けのキャンペーンは、1月〜3月の決算期と新生活シーズンに集中します。特に1月〜2月上旬に購入を確定させると、価格面でお得になりやすく、授業開始前の初期設定に十分な時間を確保できます。
まとめ|入学前に余裕を持って準備を
この記事では、大学生向けノートパソコンの選び方について、失敗パターンからスペックの見方、文系・理系別の推奨モデル、学割活用法まで解説しました:
- 5つのスペックチェックポイントを押さえる:①CPU(Core i5/Ryzen 5以上、理系はCore i7/Ryzen 7以上)、②メモリ(16GBを強く推奨)、③ストレージ(SSD 512GB推奨、最低256GB)、④重量(1.5kg以下、理想は1.3kg以下)、⑤バッテリー(実測で8時間以上)。
これらの基準を満たすモデルを選ぶことで、4年間快適に使い続けられます。
- 文系・理系別のスペックを理解する:文系はCore i5/8GB〜16GBを基準に軽量性を最優先し、理系はCore i7/16GB以上を基準に処理性能と専用ソフトの互換性(Windows)を最優先。クリエイティブ系はCore i7/32GB以上と専用GPUが必須。
学部・専攻別のスペック早見表を参考に、自分に合ったモデルを選びましょう。
- 学割とキャンペーンを最大限活用する:メーカー公式サイトの学割を活用することで、通常価格より2〜3万円節約できる可能性がある。購入時期は1月〜2月上旬が最適。
名古屋市内の家電量販店で実機を確認した後、公式サイトで学割価格を適用して購入する戦略がおすすめです。
大学生のパソコン選びは、単なる買い物ではなく、4年間の学習効率と、卒業後のキャリアに直結する重要な初期投資です。
もし初期設定や使い方で困ったら、慌てずに大学のITサポート窓口や、名古屋市内にも対応する学生サポートサービス(PCホスピタルなど)へ相談することを強く推奨します。あなたの大学生活を支える最高の「相棒」を見つけてください。
パソコンやiPhone、スマホの設定に関する
お困りごとは何でもご相談ください。
PCホスピタルのパソコンサポート

料金表
OSアップグレードも格安で設定サポート

パソコン各種設定は初期設定だけでなくOSのアップグレードなども対応しています。
OSアップグレードをしたいけど、うまくいかない方やご自分ではやったことがなくて不安な方はパソコンの専門家にお任せ下さい。
パソコンサポートでよくある依頼

- パソコンの初期設定をしてくれる業者を探している
- インターネット接続の初期設定をしてほしい
- Wi-Fiルーターの初期設定をしてほしい
- 突然ネットに繋がらなくなったので解決してほしい
上記以外にもお困りのトラブルがあればお気軽にサポートをご依頼ください。格安・安心価格にて対応しております!
メールでの ご質問 or ご相談 は24時間受付中!!
ご質問、ご相談はこちらのフォームから24時間受付中です。
※メールでご相談される方は迷惑メール設定をご確認しておいて下さい。当サイトからメールを送信できないことがございます。
参考:PCホスピタルご利用規約